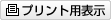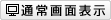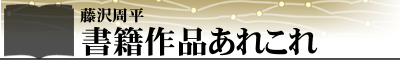- 音声ブラウザをご利用のお客様向けのリンクです。
- 本文へジャンプする
海坂藩ものにも出てくるが、『又蔵の火』の弟の心情に最も近い作品は市井ものの中に入る『闇の梯子』という短編であろう。これは昭和49年に「別冊文藝春秋」126号に発表され、同年に文春文庫から刊行されている。総じて「暗い」といわれる初期の作品群の一つで、この『闇の梯子』も結末に救いのない、暗い作品である。
主旋律は、結婚して間もない妻が、胃に腫れ物ができ、医者に死病と宣告されてしまった主人公の暗い運命なのであるが、その中に絡んで兄の話が登場する。主人公は江戸で職人として働いているが、元はといえば農家の次男で、長男を助けて田畑を耕して暮らしていた。ところが、長男である兄が放蕩の末、田畑は勿論、家屋敷も人に渡し、兄自身は行方知れずになり一家は離散する羽目となる。その兄と江戸で偶然再会するのだが、既に闇の世界へ深く足を踏み入れてしまった兄は、今度こそ弟の前から姿を消してしまう。そんな兄を回想する場面は、『又蔵の火』の又蔵(虎松)の回想のシーンにとてもよく似ている。
放蕩のあげく破産させ、一家を不幸に陥れた兄ではあるが、弟に対していつも優しかった。年が離れていたため、兄の相談役になれなかった自分。頼ろうとする者は1人もなく親類一同から白い目で見られていた兄。その兄を見ている弟の口惜しい気持ちが描かれている。この兄が屋敷にあった大きな辛夷(こぶし)の木を切っているのを、主人公である弟が見とがめる場面がある。売る物がなくなってしまって、庭の木まで売るのか、と弟は非難を口には出さず、目に表した。
その時の兄の悲しそうな表情を回想している場面は、実はエッセイ集『平生の記』の「療養所・林間荘」の章に、ほとんど同じような実話として書かれている。藤沢周平さんの実兄は勿論、放蕩したのではないが、運命の歯車の狂いで、家を破産に追い込んでしまった。そんな兄を思う気持ちが、いろいろな作品に形を変えながら吐露されたのであろう。
他にも妹を思う兄の気持ちを温かいタッチで書いた『鱗雲』や『雪明かり』『小川の辺』など数多くあり、こちらも兄妹愛をテーマにしていて情感が深い。
6人兄弟の4番目として育った小菅留治としての、人間的な心情を垣間見ることのできる作品群だと思う。エッセイ集とあわせ読むと、一層感慨深いものがある。
推奨ブラウザ
IE:6.0以上、Safari:1.2以上