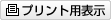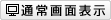- 音声ブラウザをご利用のお客様向けのリンクです。
- 本文へジャンプする

あるとき美術担当の出川三男さんが何気なくテレビを見ていると、山田洋次監督の顔がアップで出てきた。彼はぎくっとして、それから反射的に体を向き直した。
「何か要求されている」
そのときに感じる視線である。映画撮りをしていなくとも身についた適応力に苦笑いして、ギクついた神経に気がついた。若いころの監督はもっとストレートで要求度が高く、妥協を許さず、粘りに粘るキツさがあった。
「こうならないか、ああならないか」
と、本人も試行錯誤を繰り返し、執拗に注文をつけた。セットの家を造ったり、庭をこしらえたり、水を流したり、いろりの灰を用意したりと美術の範囲は広い。片桐宗蔵が鬼の爪で家老を殺し、匕首(あいくち)を墓に埋めるシーンがある。出来立ての土饅頭(まんじゅう)にすうっと刺し、石でトントン叩(たた)き、めりこませてゆく場面は故人の供養と慰霊、もっといえば剣との決別を意味する、重要なところであった。
土の抵抗に逆らいつつ、匕首を永遠の秘密として隠す。人にもらさず、秘剣のまま葬り去る。短いシーンの中に込められた宗蔵の思いは深く、自問自答するようにセリフはないのに胸内を表現する部分である。カット割りでは墓場となっており、櫛引町の松根庵で撮った。風の強い日だった。
かねて山田監督は
「日が差して晴れた空ではなく、曇っているのに弱日が差して、山が良く見える条件が欲しい」
と、指示を出していた。だが不都合にも雨が降ったり、山並みが厚い雲に覆われたり、どうもうまくゆかない。その間、スタッフたちは雲ゆき待ちで現場に待機した。
「風がでてくるとさーっと雲が晴れるんですよ」
長い間の経験で修得しているのか、監督は信じて疑わず、悠然としていた。その合間、合間を縫って、美術の出川さんはカメラに映る背景の草花をいちいち点検していた。春に咲く花を集めてきた中で色彩とか背丈とかが画面にしっくりしないものは除かれ、音が春らしく収まるように200年前の風景を演出している。
秘剣を使った宗蔵の目は、見るべき光景を見た開き直りと、ニヒリズムのような気持ちのギザギザがあって、複雑なのだ。
その当たりを周辺の空気が包み、やがてひと仕事を終え、彼が手を洗うシーンが出てくる。友人と家老を殺した宗蔵が解決しないわだかまりを持ち表現しようがないむなしさを独りごちる場面だ。
「池の水、もう少し出して。それでは出し過ぎだよ。加減してみて」
にわか造りの小さい池は出川さんの工夫で、格好の手洗い場になった。
そこで監督はマクベスに出てくるシーンのように、2人も人を殺してきた宗蔵の手は洗っても洗っても血のりが取れないようなトリックにしたかったらしい。しかし、こちらは血のりとはゆかず、土塊の汚れがべっとり付着してくっつき
「手を洗いこすっても、なかなか落ちないようにしてみて…」
と、黒墨のつき具合を幾度も確かめた。監督の思い入れにはいつも筋道がついている。
- 映画「隠し剣 鬼の爪」庄内ロケ支援実行委員会 (鶴岡市観光連盟「つるおか旅読本」より)
推奨ブラウザ
IE:6.0以上、Safari:1.2以上