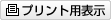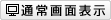- 音声ブラウザをご利用のお客様向けのリンクです。
- 本文へジャンプする

ロケ地を決めるのは、風景の目利きでなければとても決めかねる難しい視点がいる。単に
「電線がない、コンクリートが見えない、カラー張りの屋根がない」
そうした条件だけでなく、物語を進めてゆくのにイメージが膨らみ、人里のにおいが漂うようなものがないと、廃村のごとく人っ気がまったくない山道では、暮らしの温もりが出てこない。
『たそがれ清兵衛』では、葬式の行列が通る所があった。月山が寄り添い、参列者たちが続いてゆく印象的な場面だったが、今度もきえの妹のぶんが姉の見舞いにやってくるシーンに使われた。羽黒町である。監督に
「あそこが好きなんですか」
と、いう質問が飛んだ。
「羽黒町を撮りに来ているわけではなく、藤沢周平さんの作品ですからね。でも、ぼくはあの道を越えると人里がある。あの道の先に人の気配を何となく感じるんですよ」
と、監督は答えていた。
村から城下である海坂藩の町まで歩いてくるぶんには、心細くも未知の冒険に似た遠い道のりだった。一人前の大事なお使いなのである。お侍の住む城下のにぎやかさ、聞き馴れない言葉、みんな初体験となる彼女にとって、どう対処すれば良いのか、不安と戸惑いと驚きが一緒になっていたに違いない。ふろしき包みを背負い、手伝いにやってきたがすっかり気後れしてしまう。どう尋ねれば良いのか、分からない。
ぶんは子供言葉で
「ねー、ねー」
と、呼びかける。日常用語が一般化していない時代の村の子供は城下の言葉すら知らない。
「他家へ入るとき、何と言っていたの」
監督は山形県出身の助監督、花輪金一さんに問うと、彼は首をひねり
「お店へ行くときは買う、と言っていたけどね」
見知らぬ家に行くことも、正式なお使いをすることもなかった地方では、それに相当する言葉がなかなか思い当たらず難航していた。すると庄内では「ねー」と言っていたことが判明した。もはや死語になっており、身近で使われていなかったのである。
大人と子供の言葉が使い分けられており、境界線は子供は子供らしく、大人は責任をもった社会人として離反することなく仕事にいそしんでいた。生活者の法則が守られており、暮らしの感覚を映像に写し取るため、言葉や仕草が大きなポイントになる。
例えばお辞儀ひとつにも現代の若い女の子は
「ぺこりと頭を下げるだけなんですよ。お辞儀がどんなものか知りませんからね」
と、監督は嘆いていた。
ぶんが拭き掃除や洗濯をするシーンもよく説明し、足踏み洗いをした昔のやりかたをやってみせ、彼女が理解するまで指導する。しかし、こうしたやり方や家事見習い躾(しつけ)は、素養として成人した女性たちの立ち居振る舞いになっていた。
何と優雅な教養だったのだろう。
礼儀作法にある身の処し方、言葉使いに日本人が培ってきた奥行きがすがすがしく見えてくる。
- 映画「隠し剣 鬼の爪」庄内ロケ支援実行委員会 (鶴岡市観光連盟「つるおか旅読本」より)
推奨ブラウザ
IE:6.0以上、Safari:1.2以上