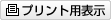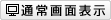- 音声ブラウザをご利用のお客様向けのリンクです。
- 本文へジャンプする

たまたま山田洋次監督を交えて、狭間弥市郎の夫婦愛が話題になった。
「鬼の爪と名づけられた秘剣をめぐる、友情と憎悪と、そして優しい愛の物語です」
江戸へたつ彼を舟着き場へ見送りに来た妻、桂は城下で評判の美人である。
つい佐門は同情心で
「1人暮らしはつらかろうのう、きれいなご新造さ置いて」
と、人もうらやむ、非のうちどころのないエリート夫婦に向かい、声をかけた。
それに応じた弥市郎は「なに、金さえあれば女はなんぼでもいるや」
と、うそぶく。当時のありふれた常識的なセリフだが、カタイばかりの宗蔵はすかさず「俺は、お前のそういうとこが気に入らねのう」
と、くぎを刺す。似た年ごろによくある突っ張りと、見栄や虚栄心を含めた弥市郎夫妻の裏側がのぞき、ここで監督は3人の若者を性格付けた。
一言、二言の会話で各自の生き方があぶり出されてくる、うまい描写である。
江戸へ上った狭間弥市郎はそこで改革派に加わり、謀反を企てるが発覚して、郷送りになる。
出世を望んだはずが逆に犯罪者となり、山小屋の座敷牢(ろう)に入れられてしまう。計算違いの人生が舞い込んでしまった。
唐丸駕籠(かご)に乗せられ、帰ってきた弥市郎のうわさはたちまち城下内に知れ渡り、元同僚たちは陰でヒソヒソ言い合っている。藩にとっても幕府表に知られないように処分するのが、ミソであった。
切腹を認めず、国元へ帰したのは酷刑なのであり、高島礼子さんが演じる妻にとっても予想外のてんまつになった。ここに及び出世の道が絶たれてしまったのを自覚せざるを得ない。そこで彼女は、人生一代の勝負にでた。
夫の命乞いに
「わたしの体を差し上げますよ」
と、討手に決まった片桐宗蔵に言い寄った。弥市郎はすでに牢破りをしており、捨て身の逆襲をかけている。どうせ死ぬならば一矢報いたい。
彼の胸には報復の思いしかなかった。
同じ戸田一刀流を学び、かつては剣のライバルだった宗蔵は藩令を受けて、弥市郎を討ちに行くが武士の名誉を重んじ
「腹を切れ」
と、勧める。だが、彼はそんな気はさらさらなく、戸田寛斎が宗蔵に授けた秘剣鬼の爪のことを口にする。長い間恨みに思っていたやりとりである。海坂藩きっての使い手といわれた弥市郎に伝授せず
「なぜお前に…」
男の嫉妬(しっと)は燃え続けていた。強気一点張りで出世欲に身を焦がし、とうとう死地へたどり着いても諦めきれず…。やるせないが、弥市郎らしい。
命乞いに来た桂を宗蔵は諌めたが、彼女は家老のところへ乗り込んでゆき、悪の上手である老練さに裏切られる。
「あの夫婦は功利的に結び付いており、夫の出世は妻の出世。その望みが絶たれたのですね」
女の計算高さをえぐりとった演出だったのである。そうでもなければ
「あの凄味はでませんよ」
三食昼寝付きの主婦の発想ではない。男の出世だけに脚光が当てられているが、一緒に生きる女もしたたかに、時には狡猾(こうかつ)さをもって世渡りしていたのである。愛の怪奇さなのか…。
- 映画「隠し剣 鬼の爪」庄内ロケ支援実行委員会 (鶴岡市観光連盟「つるおか旅読本」より)
推奨ブラウザ
IE:6.0以上、Safari:1.2以上