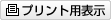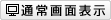- 音声ブラウザをご利用のお客様向けのリンクです。
- 本文へジャンプする

この映画で原作にまったくないものが出現したのは、軍隊であろう。藤沢文学に姿を現さなかったのが、この1点だけである。『半生の記』で作家が書いているように、予科練の試験をクラス全員で受けたことがあり
「国を憂うる正義派ぶって級友をアジったことがある」
と、告白している。それ以来、軍隊とか、陸軍とか、海軍とか、組織を成すものを避けてきた。
本人が召集されたわけではないが、長兄や村の男衆が1人、2人と抜け、耕作地が荒廃していくのを見ていた若者は自分のやった行為を恥じた。剣は書くが、鉄砲を書かなかったのは、そのあたりに原因があるのかもしれない。若く感受性の強い時期に受けたショックは比較にならないものがあったのだろう。
幕末、外圧、武士の世の崩壊と続く時代背景を分かりやすく映像化するのに、監督も考え込んだようだ。隠し剣が秘剣とされた武家社会が終わりを告げる。その大波をかぶっている地方はどんな対策を練っていたのか。とかく地方分権、合併問題が地方ニュースのトップになっている昨今に重ね合わせて見直した。
新しい改革が迫られたときの対応、人々の煮え切らなさ、旧体制へ移るときの矛盾、言うなれば価値が変わっていく過程である。刀が尊ばれていたのが鉄砲に変わり、大量の武器を持つ者が有利になる。
命がけでやってきた事柄がみんな否定され
「あれは何だったのか」
と、宗蔵のおんつぁま、片桐勘兵衛が言うように
「戦いっていうなは、刀とかやり構えて、お互い朗々と名乗り合って日ごろの修練さ物言わせて勝負する―こうでねば駄目だ」
田中邦衛さんが力説する場面まことにコッケイにみえるが、当時の多くのサムライたちがもっていた感慨である。むしろ宗蔵のようにさっさと見切りをつけ、禄を返上して侍をやめる方が珍しかったのだ。
「愛する妹を安定している友人、左門へ押し付けて、自分は外へ出てゆく。このあたりは寅さんに似ているんですが、違うのはその点ですよね」
監督は永瀬正敏さんに
「これ寅さんだね」
と、笑い話にしていた。
「先見の明がある方かもしれませんよ」
と、教官が言ってのけるのに同意する武士はいなかったのは、何を考えているのか分からない彼は、変人扱いなのであった。続いて藩士を辞める者など出てこない。寄らば大樹の陰だったのである。
皆が皆、同一価値観の中で生きている中で
「おれはやーめた」
藩命を受けるなどまっぴらだと考えた宗蔵の選択は先んじた転職だった。
常には目立たぬ男がどかーんと音をたてるがごとく変身する。スピード過剰になってしまったのだ。
「2人も人を殺し、急にいやになったんだろうね」
その気持ちと前から恋していた村娘、きえへの思いが踏ん切りになり、最終場面は監督の頭の中へできていた。
「最後は宗蔵のプロポーズにしようと…」
だが当時の求婚申し込みはどうしたのか、お見合いが常識だった武家社会の新境地開拓をどう結べばよいのか、ありきたりなものにはしたくない。
うぶな宗蔵の純愛をきえがリードするような、夫婦愛の実権をきえに握らせるような演出を考えた。
男の気持ちを本人に言わせる誘導は尋問型である。
- 映画「隠し剣 鬼の爪」庄内ロケ支援実行委員会 (鶴岡市観光連盟「つるおか旅読本」より)
推奨ブラウザ
IE:6.0以上、Safari:1.2以上