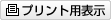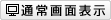- 音声ブラウザをご利用のお客様向けのリンクです。
- 本文へジャンプする

張り詰めている撮影現場にも息抜きが必要で、合間をぬって昼食に誘ったりした。連日の弁当に飽きがきたころ、あるそば屋に案内した。酒を飲まない山田洋次監督は味に敏感で、美食家ではないが味覚にこだわる人である。
ある時、スープをひとすすりして
「いいダシが効いてますね。味加減がいい」
と、味見した。そばが好きで、のどごしのよい打ち方を好み、田舎そば風な太く黒ずんだ硬い歯ごたえのあるものは苦手らしい。どちらかといえば更科好みである。
1日が日の出とともに始まり、日没で終わるような時間との追っかけっこでは、撮影中にゆっくり昼食をとっている暇がない。
撮影は太陽の陰り具合と風の向きなどによって予定が変わる。まさに大きなスクリーンに自然の営みをプリントしてゆくような作業なのである。弁当に箸をつけたところで
「やっと月山が見えてきました。用意ください」
と、いった声でスタッフ一同走り回り、配置について撮影が進行する。反対に雨にたたられて中止になった時も、強風で午後の撮影がやめになった時もあった。
日がすっかり落ち、ロケ地が闇の眠りにつけば諦めがつくが、それまでは粘りに粘るのが日課になっていた。
昼ご飯もそこそこに飛び出すことなどは珍しくなく、一刻、一刻を争うように撮ってゆく時間がまるで巻き尺のようになっている。狂いがないように正確に測り、寸法通りに合わせてゆく。思わず
「職人さんのようね」
と、つぶやくと、プロデューサーが
「まさに職人技です」
と、うなずいた。ロケ期間中に、一度は好みのそばを、プロのコツが効いた味を食べてもらいたい、そう思ったのは顎(あご)がくたびれるようなそばを食べさせた後だった。
「ぼくね、うどんでも硬いのはだめなんだよ」
庄内で食べた硬くまずいそばの印象を持ち帰られるのは、たまらない。
「名誉ばん回をしたい」
そんな話を富塚陽一鶴岡市長にすると
「それじゃ鶴岡一をごちそうしましょう」
と、富塚市長はあっさり言った。自分で食べて日本一おいしいと思ったそばを、鶴岡が開拓した打ち方で
「ごちそうしましょう」
と、請け合った。もったいぶらず、いとも気軽に自慢せずに、凡百の食通が
「うまいというそばを監督さんに召し上がってもらいましょう」
言うなれば、おいしく食べる条件をすべて持ち込み、用意した。そば粉、名人、口上を述べる人、そして食べる場の設営を整えて、その日は打ち方と食べ方を一緒にやる試食会にした。
半てんを来た田川そばグループの名人たちが駆けつけ、選りすぐったそば粉の挽(ひ)き立てを用意し、ダシは料亭の板前さんが仕込んだ味で、打ち立てを召し上がってもらう。そばの香りを部屋中に満たし、ゆでたてをさっと出す。
「これならばいけそう」
映画づくりと似て、見るからにハマリ役のごとく、名人たちは座を整えてくれた。その一部始終を見ていたプロデューサーの山本一郎さんは
「ああやって監督は職人さんたちの道具の使い方とか、身のこなしなどを学び取り、撮影に応用するんですよ」
くつろいでいるようで目はカメラに向かう鋭さを失わず、そばの功徳(くどく)はいつどんな場面に出てくるか分からない。おいしさの舌感覚を映像の中へ織り込む術も、玄妙な映画人の手の内なのである。
- 映画「隠し剣 鬼の爪」庄内ロケ支援実行委員会 (鶴岡市観光連盟「つるおか旅読本」より)
推奨ブラウザ
IE:6.0以上、Safari:1.2以上