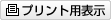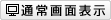- 音声ブラウザをご利用のお客様向けのリンクです。
- 本文へジャンプする

明治期に、日本が近代国家への形をととのえていく中で、農商務省は作物の生産力の増大が近代化に大変重要な役割をはたしていることにかんがみ、明治36年から国立の農事試験場で品種改良に力を入れる方針を定め、当時大阪府にあった農事試験場畿内支場において、稲と麦の品種改良に着手した。
稲を担当したのが加藤茂苞技師である。茂苞は荘内藩士・加藤甚平の長男として生まれた。明治24年東京帝国大学農学部を卒業し、同29年より農事試験場に勤務した。まず最初に秋田県大曲にあった陸羽支場に赴任した。農事試験場が東京府北多摩郡西ケ原にあった本場ではなしに、大阪府にあった畿内支場で、本場には当時温室ひとつなかったが大阪で全国博覧会が開かれた折に作られた温室2つのうち1つが、畿内支場に払い下げられていたためである。大曲にいた加藤茂苞は、安藤広太郎場長の推薦で畿内支場に移り、稲の育種を担当することになった。明治37年、初めて20組み合わせの人工交配に成功し、同41年には、交配組み合わせは235に達した。茂苞はまた、畿内支場で行った研究で稲を材料として、メンデルの法則が成り立つことを明らかにし、我が国の遺伝学の発展に貢献した。その後、茂苞は大正5年から10年まで再び大曲の陸羽支場に戻った。
これらの農事試験場の人工交配による育成種は次第に、全国で栽培されるようになるが、育種は時間のかかる事業であり、大正前期にはその成果が現場までなかなか到達していなかった。このような時期に庄内地方では、農民自身が交配方法を選び品種改良に力をそそいだが、それを茂苞は積極的に支援している。茂苞がまだ畿内支場にいた大正3、4年ころに庄内から数人の育種家は、わざわざ畿内支場まで出かけて技術を習得している。また、大正5年陸羽支場に戻ってからは、地理的に近い点もあって茂苞も庄内におもむき、また庄内の民間育種家も多く大曲を訪問して教えを受けている。工藤吉郎兵衛なども、育種材料を多く茂苞を経て入手している。吉郎兵衛が育成した「日の丸」の親になったイタリア稲の血の入った雑種や、酒米「京の華」の親となった兵庫県灘の酒米「新山田穂」などは、いずれも茂苞から提供されている。吉郎兵衛も茂苞の助力なしには、あれだけの成功は得られなかったであろう。
茂苞は、大正10年には九州帝国士学の教授となり大曲を去った。ここでも茂苞は後世に残る仕事をしている。それは、現在「印度型」、「日本型」として知られている、稲に存在している2つの大きく分けられる群の存在を、はっきりさせたことである。形態的な違いや、雑種の親和性の違いから、彼はこの2つの型の存在を初めて提案した。これは、その後の稲の種分化の研究に大きな出発点となったのである。
茂苞は、昭和3年には朝鮮総督府農事試験場技師として赴任し、さらに水原高等農林学校の校長となり、昭和9年に東京農大教授を経て昭和24年に没した。茂苞はまさに、我が国の品種改良の父の名にふさわしい人だったのである。
※原稿中の地名や年などは紙面掲載当時のものです。
プロフィール
加藤 茂苞 (かとう・しげもと)
明治元年5月17日に鶴岡の家中新町の荘内藩士・加藤甚平の長男として誕生。幼名・竜太郎。東京帝大農科大学農学科卒業。山形師範教諭を経て明治29年農商務省農事試験場技師に。本格的に水稲品種改良に取り組んだ。農試陸羽支場長となり大正8年農学博士。その間に亀の尾の食味と陸羽二〇号の多収強健性を結合した新品種「陸羽132号」を完成。冷害、いもち病に強く、品質上、倒伏に弱いが、ピークの昭和14年には東北で23万1000ヘクタールに作付けされた。九州帝大教授、農学部長、東京農大教授など歴任し、正三位勲二等を受け、82歳で死去。庄内では「もほうはん」と呼ばれていた。
推奨ブラウザ
IE:6.0以上、Safari:1.2以上