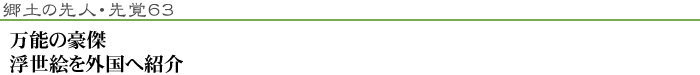- 音声ブラウザをご利用のお客様向けのリンクです。
- 本文へジャンプする

よく人生の軌跡を表現するのに「波乱万丈」とか「波乱に富む」というが、本間耕曹はその典型的人物といえよう。天保13年6月、酒田の本間家本宅で、宗家の嫡子で当時、若だんなと呼ばれていた光和の二男として生まれた。若い頃から江戸に出て、和・漢・洋の学を修めるとともに剣術を習い、のち砲術家・高島秋帆に入門して塾頭となった。手裏剣の名手でもあった。
元治元(1864)年には庄内藩から士分に取り立てられ100石を給され、江戸取締となった。慶応3年12月、江戸薩摩屋敷の焼き討ちの際には、幕府お抱えのフランス砲兵大尉某について大砲の配備などの指導を受け、その作戦を練った。現在、光丘文庫に彼の蔵書の一部が残されているが、そのほとんどは砲術や西洋兵式の本であることからみても、彼がいち早く西洋兵式を学んでいたことが知られる。
明くる4年には砲術方として藩の軍艦・奇勝丸に乗り組んでいる。同年5月、戊辰戦争を目前にして北海道から庄内藩兵700人余人がドイツ人アカハネ・スネルの蒸気船ロバ号で酒田に帰った。このとき函館商人・柳田藤吉の仲介でスネルから銃器弾薬の買い入れ契約を結び、7月酒田港に運ばれている。買い入れ人は本間家で総額3万4533両を8月2日にスネルの代人文蔵と清次郎に渡している。彼らの船宿は秋田町にあった永田茶右エ門である。
明治5年9月から翌7月まで、東本願寺法主・大谷こうえい氏に従って渡欧した。30歳のときである。一行はすべてエリートでのちに各界で指導的役割を果たした人が多い。たとえば仏教界の石川舜台、明治憲法制定に貢献した井上毅、自由民権的フランス法学者・沼間守一、新聞界の先覚者・成島抑北、警察行政を確立した川路利良などである。彼らは向こうではそれぞれ自由に行動し新知識を吸収した。帰朝すると彼は政府に鉄道敷設の必要性を説いた。
同8年には兄光貞(山手の本間)が本家を継ぐべきだと相続争いを起こしたが、翌9年10月、三條太政大臣などの仲介により和解した。同10年警視庁に入り大警部、2等警察使になったが18年退職。25年改進党から出馬し衆議員議員となった。甥の本間光義、池田藤八郎も衆議員議員である。
27年以降東京小石川に住み骨董商を営み、浮世絵を外国へ紹介した。しかし、すでに同22年に息子・光則の名で『浮世絵類考』を出版しており以前から美術趣味があったことを示している。耕曹はまさに酒田が生んだ知られざる万能の豪傑である。
※原稿中の地名や年などは紙面掲載当時のものです。
プロフィール
本間 耕曹 (ほんま・こうそう)
酒田の生まれ。若いころ江戸に出て、庄内藩の江戸取締などを経て慶応4年砲術方として同藩の軍艦「奇勝丸」に乗り組んだ。明治6年にドイツのベルリンに行って9カ月間滞在、その後警視庁にはいり、警視兼2等警察使を経て同18年に退官。25年から27年まで衆院議員(改進党)。同42年、兄光貞の病気見舞いに帰郷した後、鶴岡で急逝した。享年68歳。酒田市の浄福寺に埋葬された。