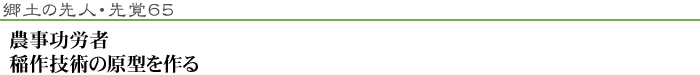- 音声ブラウザをご利用のお客様向けのリンクです。
- 本文へジャンプする

杉山良太さんは、話しても第一人者、黙っていても第一人者、踊っても歌っても第一人者であった。もちろん、稲、杉林を育てては名人と称された精農家である。
明治32年、酒田市旧本楯村、何世代続いたか不明というが、寅吉の二男として生まれ、少年時から田の草取りなど手伝い、小学校を卒業して家業につき、17、18歳の2カ年は見習い奉公として他家の飯を食う。19歳にして父から2.6ヘクタールの稲作りをまかせられたが、「でって、なんにも教えてくれなかった」。杉山さんの百姓としての取り組みがここから始まる。大正6年のことである。
このごろ、“米”が厄介者扱いにされるきらいがあるが、日本の2000年の歴史は、米(食糧)の生産量をどう高めるか、との2000年であったといっても過言ではあるまい。
戦時中平時の3~5倍も食糧を必要とする昭和17年「食管法」が施行されたのもどう生産を高め、国民平等に食せるかにあった。戦中、戦後の生産者への米の割り当て供出は苛酷を極めた。昭和16年からの7年間、杉山さんは部落実行組合長として生産から供出までの責を負う。当時、本楯倉庫長・林友次郎氏などの仲間と共に、稲作りの勉強と実践を積み重ねた杉山さんは、昭和14年から反当(10アール)10俵(600kg)平均を挙げていた。6俵以下の生産しかなかったころのことであるから、その実績の持つ意味は大きい。
割当量以外の米は3倍価格で売れる報奨制度もあったが、杉山さんはそれには目もくれず、「ありったけの米を出してしまう」ことで近隣の信望を一身にあつめる。
農協が設立されると理事に、荒れた森林組合の立て直しに理事に選ばれ、旧村の財産管理の要職を20数年にわたって努めた。絶大な信頼である。じっと耳を傾けて、杉山さんの話を聞くといい。それは謙遜した本当におとなしい話であるが、ビシッと要点をつき、聴く者の胸をうつ。単なる机上の勉強だけではなく、体験からにじみ出た話で古酒のように後味がいい。そして黙っていても第一人者なのである。
飽海郡指導員に任命され、気軽に庄内や近県の田を見て回った。「わたしはわたしの田しか、つくったことがない。わたしの農業を鵜呑みにするのは危険だ」だが、その技術は県の奨励となり、今日も脈々と生き輝いている。
昭和37年に「緑白綬有功章」、39年に「黄綬褒章」が授与された。
※原稿中の地名や年などは紙面掲載当時のものです。
プロフィール
杉山 良太 (すぎやま・りょうた)
農事功労者。本楯の生まれ。19歳で稲作の家業を継ぎ、やがて、1.3ヘクタールから2.6ヘクタールに規模拡大。稲作を子息・弥一さんに譲ってからは自家林、部落有林、組合林など杉林の造成に貢献した。地域の有志で天狗会を組織して農村の人材確保と農業の基盤の米生産を研究。特に基肥だけの施肥方法に疑問を抱き、平均600kg以上の高収に取り組み、今日の稲作技術の原型を作った。受章の推薦で県の係員が「たいした肩書がないのでは…」と渋ったが、「広く農民や地域のために尽力したことが貴重では」と地元民の推薦が受け入れられた。