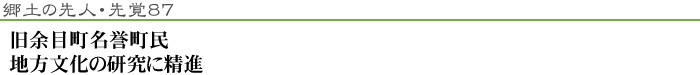- 音声ブラウザをご利用のお客様向けのリンクです。
- 本文へジャンプする

「佐藤東一氏は、今大学の講壇に立っても第一級の教授として尊敬されるであろう」
これは晩年の佐藤氏と親交のあった宇佐美繁宇都宮大学教授の言葉である。佐藤東一氏は明治29年12月8日、余目町(現・庄内町)の名望家佐藤清太氏の長男として出生した。大正4年3月、県立荘内中学校を卒業した佐藤氏は、向学の志止み難きものがあったが、当時家督を継ぐ身には許されるべくもなかった。その失意の心に光明を与えたのは、大正12年6月発行の雑誌・中央公論に掲載された早稲田大学教授・内ケ崎作三郎氏の論文であった。
“地方に於いて父親の業を継ぐ中学卒業生は、地方文化運動の指導者たれ、地方文化史の研究者たれ”
この論文を読んだ佐藤氏は、初めて家業に専念する決意とともに、生涯の指針として地方文化の研究に精進することを固く心に期したという。決意を新たにした佐藤氏が、当時特に感銘を受けた本として、次の2冊をあげている。
京都大学教授・本庄栄治郎氏著『近世農村問題史論』、農学博士・小野武夫氏著『郷土経済史研究提要』である。
郷土研究を決意した佐藤氏が、先覚者として指導を仰いだのは、隣町松山町(現・酒田市)の阿部正巳氏であった。阿部氏は文学博士・喜田貞吉氏とも親交があり、郷土史の泰斗として全県下にその名が聞こえていた。佐藤氏自身の言によれば、郷土研究の方向として民俗学に力を注ぐべきか、または歴史学によるべきか迷うことがあったという。阿部氏との出会いはこのことに結論を見出したといえよう。昭和7年秋のことであったという。
以来佐藤氏の鬼気迫るばかりの勉学が続けられる。対象は古文書学、仏像、甲冑、建築、彫刻など歴史関係全般に及んだ。特に甲冑、仏像に関して、その学識は専門家の域に達し、県の文化財専門委員に委嘱されている。また、次にあげる主な著書は後学の者にとってかけがえのない指針となっている。
『荘内の文化遺産』、『庄内の金工』、『庄内の鎧』、『庄内の仏像』、『最上川土地改良区史全5巻』
最上川栃改良区史は、北楯大堰に関連する資料の集大成で、4000ページ余もある膨大なものである。
こうした佐藤氏の業績に対し、数々の栄誉が授与された。
- 第2回高山樗牛賞(昭和34年)
- 勲五等瑞宝章(昭和43年)
- 斎藤茂吉文化賞(昭和44年)
- 清河八郎文化賞(昭和46年)
※原稿中の地名や年などは紙面掲載当時のものです。
プロフィール
佐藤 東一 (さとう・とういち)
郷土史家。大正4年旧荘内中学校を卒業し、松山町出身の史家・阿部正巳の指導を受けて郷土史を研究。その研究は甲冑武具にもおよび、幅広い。地元の古文書類、神社仏閣、彫刻の調査も有名。昭和28年に県文化財専門委員に委嘱され、余目町教育委員も務め、54年には名誉町民。文化功労の功績が高く評価されて各種表彰、叙勲を受けている。著書も多数。89歳で死去。