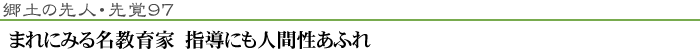- 音声ブラウザをご利用のお客様向けのリンクです。
- 本文へジャンプする

斎藤七郎氏は明治29年山形師範を卒業、余目小学校勤務、翌30年10月から大正14年7月まで同小学校の2代目校長になった。その間29年も校長というのはいかに昔であっても珍しく、このような長期間の同一校の校長であれば、とかく教育界、地域の大ボスとか、教育のマンネリ化にもなりやすいものであるが、いっさいそういう点はなかった。
それどころか、大校長として地域の人達に尊敬され、期待もされていた。またそれにふさわしい新しい事業を完成して余目の教育を発展させた。
その内容をみると、
- 校舎の移転改築2回
- 校友会の設立
- 夜学校新設
- 女子教育普及運動
- 貧困で就学が容易でない児童のために学齢児童保護会創立
- 学校と家庭の連絡をはかる学校と保護者の懇話会(保護者の出席率が90%以上にも達した)
- 村立図書館を小学校に創設
- 余目育成会創立
などである。
教育だけでなく、社会の諸問題についても見識高く、論説、批評、提言、随想などで活躍した。それらは時代を越えて現代にも生きている。
大正14年に余目小学校の職員心得を寄稿した。玄関から玄関までという題で、普通心得といえば堅苦しく、何々すべしといった命令調であるが、この文には教員のあるべき姿が具体的に、平易に、ユーモアも感じさせられる。
次に最後の紹介すると-斯くて一日の業終わり、後始末をなし成るべく早く退散して親子兄弟乃至購入書の顔を見或は余技に遊ぶも亦床し-。これは今日の教師にも大いに参考になると思う。
氏は非常な勉強家でもあった。教育科文検にも合格し、上級学校からの勧誘もあったが断り、すべて郷土の余目小学校に専念した。
権力におもねず、また部下思いで、児童からも「ヒゲダダチャ」と親しまれ、担任がいないとかわりに教室にでかけていった。昼食時に、なっぱ塩づけで包んだにぎりめしを火鉢にあぶって食べた。
よく口にされたことは「かわいくば五つ教えて三つほめ、二つ叱りてよき人にせよ」ということであった。大正4年には今で言う教育目標のような児童訓、良き余目人をかかげた丈夫な身体、立派な精神をつくるために、具体的にはきれいにせよ、病気にまけるな、正直にやれ、人にたよるなといったようなことが述べてあり、これらが成績表の裏表紙に印刷されていた。
単なる地域の教育家ではなく、全国的にもまれにみる名教育家であり、全国教員大会では京都大学総長・沢柳政太郎氏と、視学制度の改善について堂々と論陣をはって一歩も譲らなかったこともあった。
※原稿中の地名や年などは紙面掲載当時のものです。
プロフィール
斎藤 七郎 (さいとう・しちろう)
明治8年8月、東田川郡新堀村大字局に生まれた。余目小学校高等科第三学年を修業し、局小学校授業傭になって教壇に立った。明治29年師範卒と同時に余目小学校に勤務。大正14年の死去まで実に30年間、終生同一校であった。その間、町、郡、県から表彰されること5回。大正8年には文部大臣から小学校教育功績によって選奨された。氏の偉大な功績について、余目小学校校友会が昭和2年に建設した功徳碑の銘には「資性豪邁闊達ニシテ才幹衆ニ絶ス-遂ニ逝ク享年五十有一、町民子弟慟哭セサル者無シ、涙ヲ揮シテ町葬ノ式ヲ行ヒ」と記してある。