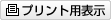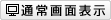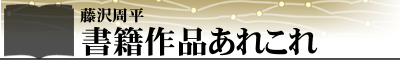- 音声ブラウザをご利用のお客様向けのリンクです。
- 本文へジャンプする
藤沢周平文学に教えられること(中)
『用心棒日月抄』という作品があります。これは以前、NHKで「腕に覚えあり」というタイトルでドラマ化し、放映されていますが、その原作です。この作品の主人公は青江又八郎という、背が高くて美男子でとてもさわやかな印象を与える青年剣士です。この前途ある青年が偶々藩の上層部の権力争いに巻き込まれ、やむなく脱藩して江戸へ逃れます。北の方にあるその故郷の藩には年老いた祖母(両親は既にいない)や許嫁をのこして、江戸で浪人暮らしをするのです。持っていった金が底をつき、口入れ屋(これは現代でいうと人材派遣会社のような、私設の職安のような所で、奉公口の周旋をする店ですが)へ行き仕事を探します。剣の腕前を買われて用心棒として雇われるのですが、これは武士にとって情けない商売なのですね。雇い主は町人であることが多く、中には犬の用心棒というのもあり、体面を考えればやってられないような仕事です。おまけに国許からは次々と刺客が送り込まれ、命を狙われます。これは考えるととても理不尽なことです。本人は権力争いとは全く関係のない下級の士(さむらい)なのですから。さらに、権力争いをしている当の家老の1人から国許に呼び戻され、藩主の毒殺を謀った一味の首領格の男を討てと命ぜられ、死闘をくりひろげるのです。その結果、藩内の抗争はいったん収まりを見せるのですが、命を賭けて剣をふるった主人公には、ほとんど褒美らしいものも出ません。こんなワリの合わない任務を、なぜ主人公は引き受けるのでしょうか。武士として忠義を尽くすのは当たり前、藩のために死ぬのは当然、といえばそれまでですが、この青江又八郎のような生き方は一種独特の雰囲気を感じさせます。そして、これは藤沢さんの作品に登場する主人公に共通の生き方だと思うのです。それはどういうものか-あえて申し上げれば、諦念(ていねん)というか、運命を受け入れて、それに静かに向き合う生き方、というようなものではないか、と思います。
損得を抜きにして、自分の定めに対し誠実に向き合う男の潔さがそこにはあります。自分の得のためにしゃにむに進むことも人間には時には必要なことですし、これを否定はしませんが、今の世の中を考えると私たち現代の人間はあまりにも得の方向にのみ進みすぎて目がくらんでいるのではないでしょうか。「耐えること」を忘れ、すぐ「頭に来た」と言い、自己中心的に行動して周囲の人を傷つけていることが多いと思います。このような主人公の生き方を見るとき、自分たちの生き方の貧しさを反省させられてしまいます。
「耐えることの大切さ 藤沢周平文学に教えられること(下)」へ続く
(1997年4月 鶴岡ロータリークラブ講演より)
推奨ブラウザ
IE:6.0以上、Safari:1.2以上