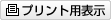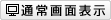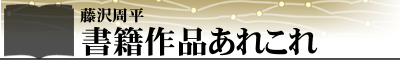- 音声ブラウザをご利用のお客様向けのリンクです。
- 本文へジャンプする
しかし、表面上はあくまで従順に夫の命令を聞く路である。路は家の中でも決して夫への不満を悟られないようにしている。武家の妻として抑制しながら生きてゆくのであるが、その夫と、夫の背後にある権力に対し、ただ一度逆らった。父の弟子であった曽根兵六という男を助けるためである。兵六を暗殺してしまおうとする企みを事前に知った路は、密かに行動し、無事に成し遂げるのである。路の心には、娘時代までの自分、すなわち、父・兄・妹、曽根兵六らと過ごした日々が過ぎ去り、なにかが終わってしまったのだ、という思いがよぎる。終わってしまったもの-それは人の心が寄り合う、ぬくもりのある家庭、とでもいったらいいのだろうか。今は違うかぜが吹いている自分の家を、妻として守らなければならぬ立場にある路の孤独感が胸に迫る。この作品の終わりの数行は、抑制の効いた名文であり、読む者に路のさびしさが迫ってくる。表向きは幸せそうな家庭にいる路と、貧乏人の子だくさん家に嫁いだ叔母とを比べている点も効果的で、路をはじめとする家の幸、不幸の不確かさが感じられてならない。
「不幸せな女(3)」へ続く
(筆者・松田静子/鶴岡藤沢周平文学愛好会顧問)
Loading content - please wait
推奨ブラウザ
IE:6.0以上、Safari:1.2以上
推奨ブラウザ
IE:6.0以上、Safari:1.2以上