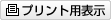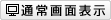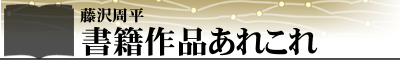- 音声ブラウザをご利用のお客様向けのリンクです。
- 本文へジャンプする
『三ノ丸広場下城どき』の茂登は37歳。30歳の時に夫に死なれ、子供がなかったこともあって婚家を出された。実家は300石の上士の家で、出戻りの女を面倒見るぐらいは何でもない。しかし、茂登は10代や20代の若い女ではなく、当時の感覚ではもはや中年を過ぎた女である。そういう出戻りがいることを世間体が悪いと気にする実家はどうみても居心地のよいわけがない。しかも、実家の当主は既に父から兄に代わっている。嫂(あによめ)への遠慮もあろう。
それやこれやの事情から、茂登は遠縁にあたる粒米重兵衛の家に「手伝い」と称して遣られる。重兵衛は42歳。妻に病死され、幼い女の子を抱えたやもめ暮らしの男である。茂登はこの家の主婦代わりをさせられるのだが、こんな都合よく他家へやられた女の気持ちはどんなものだろうか。「女は三界に家なし」という言葉が残酷に胸に響いたことだろう。
ところが、茂登は不満を言うこともなく、重兵衛や娘の世話をし、家を守ろうとする。この茂登の心情にはいたく興味をそそられるものがある。まず、想像されるのは、あきらめの心境であろう。帰る場所のない女の仮の居場所として重兵衛の家にいるということである。しかし、それだけでは茂登の献身ぶりは納得できない。茂登は、妻に先立たれ、うらぶれている男と、幼い娘に同情した。これもあるだろう。しかし、それでもなお理解し難い。
「不幸せな女(6)」へ続く
(筆者・松田静子/鶴岡藤沢周平文学愛好会顧問)
Loading content - please wait
推奨ブラウザ
IE:6.0以上、Safari:1.2以上
推奨ブラウザ
IE:6.0以上、Safari:1.2以上