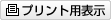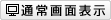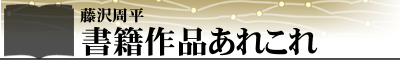- 音声ブラウザをご利用のお客様向けのリンクです。
- 本文へジャンプする
この重兵衛という男は若いころは剣で名をあげたが、今はある失策が因で100石も禄を減らし、わずか65石の御馬役である。年中馬小屋にいるため、馬の匂いがしみついている。しかも、夜な夜な飲み屋で酒浸りの生活がたたり、腹も出てきた。情けない中年、いや初老の男である。そういう男であるにもかかわらず、茂登は重兵衛を憎からず思っているようである。実家から再婚話があったときも断っている。
しかし、屈折した中年男女であるから2人の仲は全然進展しないまま、5年も経つのである。さらに、茂登には秘密があった。女だてらに怪力の持ち主だというのである。片手で梳きかけの髪の髻(もとどり)を持ったまま、もう片方の手で重い石うすをひょいと持ち上げるほどの力である。男だったら、この怪力も長所となるのに、女である茂登にとっては、ひた隠しにするほどの悲劇のタネなのである。怪力女ということが知れたら、気味悪がられるばかり、茂登はそういう女だった。
この2人が結ばれるまでの紆余曲折をくだくだ述べるのは控えるが、重兵衛がそれまでのぐうたら生活をやめ、茂登を大切にするようになるために、作者はひとつの事件を用意する。事件は2人の信頼と絆を強める仲立ちとなっている。
あきらめの中にあっても、真心を尽くし、ひっそりと生きてきた茂登の余生は、きっと穏やかで満ち足りたものになるだろう。そう予感させてこの物語は終わっている。
「不幸せな女(7)」へ続く
(筆者・松田静子/鶴岡藤沢周平文学愛好会顧問)
Loading content - please wait
推奨ブラウザ
IE:6.0以上、Safari:1.2以上
推奨ブラウザ
IE:6.0以上、Safari:1.2以上