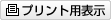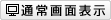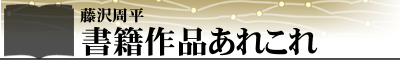- 音声ブラウザをご利用のお客様向けのリンクです。
- 本文へジャンプする
『又蔵の火』では、史実に沿いながらも、兄を思う又蔵の気持ち、兄の仇を討たなければならないという暗い情念の炎を中心に小説化されている。万次郎・虎松兄弟は父、土屋久右衛門の妾の子どもとして生まれ、血のつながらない兄、土屋才蔵に引き取られて育った。万次郎はゆくゆくは土屋家を継ぐ者として期待され、頭も良く、剣の腕も良かったのに、次第にぐれてゆく。放蕩のあげく、座敷牢に入れられてしまうのである。弟の虎松は万次郎より4つ年下であり、兄とは違って無口でおとなしい性格である。座敷牢から兄を救い出し、2人で脱藩するのであるが、途中で藩へ引き返してきた万次郎が、引き取りにきた土屋丑蔵(才蔵の娘婿)らに斬り殺されてしまう。そのことを伝え聞いたときの虎松の憤怒が抑圧され、胸の中に熱く鬱積される場面がこの小説のヤマ場である。
兄は確かに土屋家のもて余し者だった。どうしようもない遊び人で、父が心配しながら死んだ後は家の財産を傾けてしまいそうな放蕩ぶりだった。誰もその死を悼む者はなく、むしろ厄介払いができたと思っているだろう。しかし、と弟の虎松は思う。兄には兄の言い分があったはずだ。兄に代わって、一言言うべきことがある、と虎松は口惜しく思い、自分が若くて何もしてあげられなかった無力さが情けないのである。放蕩する姿の裏に潜んでいた兄の悲しみを知っているのは自分だけだった、と虎松は兄の落ちた地獄の深みを測るのである。
この総穏寺仇討ち事件の真相は謎が多く、相討ちの2人が「義士」と扱われるようになった経緯なども不思議な点が多いが、『又蔵の火』では、兄の仇を討とうと激しい闘争心を燃やした弟の心情に光を当てて、この事件を切ってみせている。その執筆の動機について、藤沢さんの教え子の万年慶一さんは「ご自身のお兄さんに対する思いを描きたかったのではないか」と仰った。実兄に対する弟・小菅留治としての思いを小説を介して述べている一面がある、と。そう言われてみると、『又蔵の火』以外にも似たような心情が述べられている作品があった。
推奨ブラウザ
IE:6.0以上、Safari:1.2以上