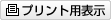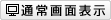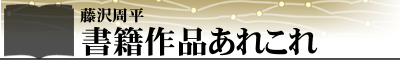- 音声ブラウザをご利用のお客様向けのリンクです。
- 本文へジャンプする
その権兵衛を利用したのは、藩の権力者であった。禄を戻してやる、との甘言に、一か八かの賭けをする権兵衛。それを止めようと説得する他の2人。その3人が最後に会った場所は、「むじな屋」という居酒屋で、肴は鰊(にしん)と大根の古漬けであった。
権兵衛は罠にはめられて命を落とし、その罠をしかけた大物を他の2人が闇討ちする、という展開なのだが、この小説の面白さは3人の悪相をした老人たちのキャラクターにあるといってもよい。藩の権力争いのパターンは他作品と似ている。命がけで闘うのは身分の低い武士で、それを利用しながら出世したり、政敵を陥れたりするのは権力の中枢にいる人である。「海坂藩」の下級武士の憤懣は、一杯飲み屋で吐き出される、というわけで、現代のサラリーマンに共感をもって読まれるゆえんもこの辺にあるのだろう。『闇討ち』の3老人の飲み屋における話やしぐさがユーモラスな中に哀しみを漂わせる。とりわけ、権兵衛は死に、2人がその仇を討ち、その仇討ちも結局は権力闘争にうまく利用される形で収拾されてしまったあとで、残った2人が飲み屋に行こうとするときの会話に、「残日」の哀しみをにじませる。この辺りの文章の魅力が藤沢文学の真骨頂を示しているといえよう。
余談であるが、三屋清左衛門も、刈谷範兵衛も妻に先立たれ、寂しい老後ではあるが、幸いに嫁が優しく、舅を敬愛し、理解している。『闇討ち』に登場する3人の老人のうち興津三左衛門の妻も5年前に病死している。嫁の加弥は興津を敬い、懸命に世話をする。前の2作品と設定が似通っていて、どうやら「老人力」を支える一つの役割として嫁の存在がパターン化されて存在するらしいことに気がついた。
(筆者・松田静子/鶴岡藤沢周平文学愛好会顧問)
- フリーペーパー

気になるお口の健康について、歯科医の先生方が分かりやすく解説します- 特集企画
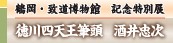
酒井家庄内入部400年を記念し、徳川家康の重臣として活躍した酒井家初代・忠次公の逸話を交え事績をたどる。
酒井家庄内入部400年を記念し、庄内藩中興の祖と称された酒井家9代・忠徳公の業績と生涯をたどる。
江戸幕府が3大名に命じた転封令。幕命撤回に至る、庄内全域で巻き起こった阻止運動をたどる。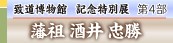
酒井家3代で初代藩主として、庄内と酒井家400年の基盤を整えた忠勝公の事績をたどる。
幕末~明治・大正の激動期の庄内藩と明治維新後も鶴岡に住み続けた酒井家の事績をたどる。
酒井家が藩主として庄内に入部し400年を迎えます。東北公益文科大学の門松秀樹さんがその歴史を紹介します。
教育現場に身を置く筆者による提言の続編です。
子どもたちを取り巻く環境は日々変化しています。長らく教育現場に身を置く筆者が教育をテーマに提言しています。
鶴岡市櫛引地域出身の大相撲の元横綱・柏戸の土俵人生に迫ります。本人の歩み、努力を温かく見守った家族・親族や関係者の視点も多く交えて振り返ります。
藤沢周平作品の魅力を研究者などの視点から紹介しています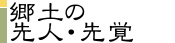
世界あるいは全国で活躍し、各分野で礎を築いた庄内出身の先人・先覚たちを紹介しています
旬の食べ物を使った、おいしくて簡単、栄養満点の食事のポイントを学んでいきましょう
庄内の「うまいもの」を関係者のお話などを交えながら解説しています