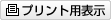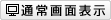- 音声ブラウザをご利用のお客様向けのリンクです。
- 本文へジャンプする

長い1本のフィルムを撮り終わり、クランクアップを迎えたのは5月13日だった。最終撮りを終えて監督が1人ひとりの労をねぎらった。
みんな休みを返上し、スケジュールをやりくりしてきた疲れがどっと出る瞬間である。
「終わったぁ」
ここで関係者一同は解放されるが、監督には編集と音入れの仕事が残っている。締めくくりの作業であるが、こちらは別で、共同の作業はここまでなのだ。スタッフの1人、相場貴和さんはそれから一昼夜ではなく、二昼夜眠り続け、ベッドから起き上がれなかった、という。かなりきつい、通しの肉体労働であった。
撮影中は緊張してスタンバイしていたのに、解放されてタガがはずれ、それがたるみになってぐったりするのかもしれない。
各自の思いが積み重なった作品、仕上がりを待った。中にはエキストラで出演した人もいる。担当を離れ、「役者」として出演、映画の巻末に名前が出てくる。
「あれね、最後に名前がでてくるでしょ。みな映画館では席を立たないで見てくれるんですよね。時には拍手が沸き起こったりして」
つくり手としては観客の反応が気になる。後ろの席で見ていると
「思わぬところで笑ってくれたり、いちいち反応してくれるのよね」
真っ暗い館内で、配給会社松竹のマーク富士山が出て、やがてタイトルに続き、ファーストシーンが映し出される。
芝居やコンサートにはない、スクリーンの迫力、映像の持つ力強さ、音楽が包み込む風景と配役の誘い。気持ちが高ぶり、画面へと吸い込まれていく。家庭のテレビでは絶対に味わえない。
「スピーカーのボリュームはすべて館内に合わせてつくってありますからね。音響はいいんですよ」
映せばいいのではない。総合芸術として制作された意図を満足させる仕掛けが必要なのである。「隠し剣 鬼の爪」では生オーケストラの吹き込みをやり、主人公の旅立ちにふさわしい大地の明るさを思わせるよう、緑がさやぐ爽やかさでエンディングを演出した。
カメラワークでいつも信頼を置いている長沼六男さんに、監督がラストシーンのきえ(松たか子)の表情を尋ねていた。
「どうでした」
「ほんと、いい顔でしたよ」
それを聞くと、にこやかに活気を帯びた表情になり、筋書き通りの出来に安心したようだった。
江戸時代のプロポーズはどんなふうにしたのか、また答える方も歯切れ良く返事をしたのか、口ごもったのか、どっちにしても文献がない。
小説通り、途中までは
「おれはお前が好きだ。お前はおれを好きか」
「そんなことは考えたこともありません」
と、原作に従った。その後転じるやりとりは
「ぼくが考えたのです。宗蔵に好きだと告白されたきえは余裕を持ち、優位に立ってこの決定権は宗蔵に握らせた方がいい。そうした計算のできる賢い女性だったと思うのね。そこでそれはだんなさんの命令ですか、と彼女はからかったわけです」
現代風に解釈すれば、武士を辞して町人になった男は、村娘のきえと同等なのになぜ雇用者と使用人の関係になるのか、疑問に思う人がいるかもしれない。
当時の男女の会話に
「愛してます」
などという、常とう恋愛用語はなく、好き嫌いの二語の中から選択するならば、返事は
「好きです」
と、断言してしまうのはあまりにも色気がない。
キャッチボールのように投げ返して、宗蔵に言わせてしまう。ここに主導権をとった女性の巧みさがあり、男を心地よくのせ、勝ちを譲ったのだ。
「この後宗蔵は尻の下に敷かれたでしょうね」
結婚生活は平穏で、しかもこの関係は孫ができるまで続き
「おじいちゃんとおばあちゃんはどうして結婚したの。おじいちゃんがプロポーズしたの」
と、聞かれるたびにきえが答える姿を監督は想像し、にんまりするそうだ。映画には大抵、画面に出ない落ちが隠されてある。
- 映画「隠し剣 鬼の爪」庄内ロケ支援実行委員会 (鶴岡市観光連盟「つるおか旅読本」より)
- フリーペーパー

気になるお口の健康について、歯科医の先生方が分かりやすく解説します- 特集企画
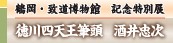
酒井家庄内入部400年を記念し、徳川家康の重臣として活躍した酒井家初代・忠次公の逸話を交え事績をたどる。
酒井家庄内入部400年を記念し、庄内藩中興の祖と称された酒井家9代・忠徳公の業績と生涯をたどる。
江戸幕府が3大名に命じた転封令。幕命撤回に至る、庄内全域で巻き起こった阻止運動をたどる。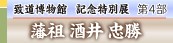
酒井家3代で初代藩主として、庄内と酒井家400年の基盤を整えた忠勝公の事績をたどる。
幕末~明治・大正の激動期の庄内藩と明治維新後も鶴岡に住み続けた酒井家の事績をたどる。
酒井家が藩主として庄内に入部し400年を迎えます。東北公益文科大学の門松秀樹さんがその歴史を紹介します。
教育現場に身を置く筆者による提言の続編です。
子どもたちを取り巻く環境は日々変化しています。長らく教育現場に身を置く筆者が教育をテーマに提言しています。
鶴岡市櫛引地域出身の大相撲の元横綱・柏戸の土俵人生に迫ります。本人の歩み、努力を温かく見守った家族・親族や関係者の視点も多く交えて振り返ります。
藤沢周平作品の魅力を研究者などの視点から紹介しています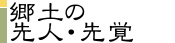
世界あるいは全国で活躍し、各分野で礎を築いた庄内出身の先人・先覚たちを紹介しています
旬の食べ物を使った、おいしくて簡単、栄養満点の食事のポイントを学んでいきましょう
庄内の「うまいもの」を関係者のお話などを交えながら解説しています