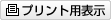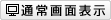- 音声ブラウザをご利用のお客様向けのリンクです。
- 本文へジャンプする
荘内日報ニュース
2009年(平成21年) 3月13日(金)付紙面より
ツイート庄内浜のあば 悲哀と快活と歴史と ―1―
浜で水揚げされたばかりの魚を売り歩く行商の女性。バイタリティーあふれる姿に、人々は「浜のあば」と親しみを込めて呼ぶ。まんじゅ笠をかぶってリヤカーを引く姿は、城下町・鶴岡市の風情によく似合う。藩政時代に始まり、食糧難の戦後は家庭の食卓を支えた。自分の体重より重い荷を背負い、言葉づかいは快活なあばだが、人に言うに言えないつらさを胸に秘めた人も多かった。そんなあばたちの悲哀・たくましさ・行商の歴史をたどってみた。
消えいく“食文化の配達人”
「あば」とは
「あば」。かつては庄内地方でごく日常的に使われていた母の呼称だ。今この言葉を耳にすることはまれになり、「あば」と呼ばれるのは、魚をリヤカーに積んで檀家(だんか)(得意先)を回って売り歩く行商の女性を言い表す意味合いとして残る。
「あば」を漢字でどう書くのか。地方出版物などには「阿婆」、「海女」、「若母」、「小母」が見られるが、いずれも当て字と思われる。
「あば」を辞書で引くと、出ているのは「網端(あば)=うき」。網の端を意味することから、魚網に付けるガラス球や樽(たる)のような「浮き」を指し、庄内でいうあばとはまったく違う意味だが、海と魚に関係している点では共通する。
妻であり母であり
あばについて、元県立鶴岡南高校教諭の富塚喜吉さんは『月刊庄内散歩』(東北出版企画)の「庄内女風土記」で、次のように書いている。
「『温海土産(安政4年、作者不詳)』という膝栗毛もどき滑稽(こっけい)本の中に『あばと申すは、すべて夫ある女を申す也』とある。しかし、おらえのあばと言った場合は自分の妻を指し、男が未婚であれば自分の母を意味する。街に住む者にとって、あばは蔑(べっ)称のように響くが、庄内浜では「シンショウ」(財布)を握る誇り高き主婦の座であり、語感が示すそのままに、たくましく生きる女性の呼称である。ともあれ、『あ』と『ば』が協和するエネルギッシュなこの音楽は、潮風に乗ると、そこはかとなくノスタルジアをくすぐるから妙である」と。
また、『酒田地方方言集』(斎藤邦明編)では「あば=魚売女」と、ずばり行商の女性だと記述している。
浜で捕れた魚を消費者に届けるあばは、新鮮さが自慢の産地直送(直売)の先駆けだった。まんじゅ笠をかぶり、リヤカーを引いて街を歩く姿は城下町・鶴岡の風情に似合っている。鶴岡市出身の作家、藤沢周平さんも短編小説『玄鳥』で、〈城下には朝のうち漁師の女房が魚を売りにくる〉と書き、『龍を見た男』の油戸の漁師の女房も、山を越えて城下まで売りに来た。
また、エッセーでは〈子供時代に威勢のいい浜の女子衆(おなごしょ)が、荷を担いで魚を売りに来た。筋子、塩引きの鮭、干鱈(ひだら)、身欠きニシンなどの塩干物を背負って来た〉と懐古している。
90歳に届く現役も
最盛期、庄内全域で800人を超すあばが活躍した。終戦直後は警察の取り締まりを受けながらも魚を運び続け、庶民の食卓を支えた。それもスーパーと車社会に押されてすっかり存在感が失われてしまった。
あばは一代限りの商売。今も90歳に届こうというあばもいる。しかし、見栄えが良くないことや、行商人登録の条件も厳しくなってこの道に入る人はいない。高齢化から年を追うごとに引退する者が増え、あばという言葉が日常的な会話から遠ざかっていくように、昔ながらの風情を残す“食文化の配達人”は、いずれ姿を消す運命にある。
(論説委員・粕谷昭二)

行商を終えて列車から降り、帰宅するあばたち=温海駅(現あつみ温泉駅)前で。昭和30年代前半・鶴岡市温海庁舎提供=(左) 狭い路地での行商。リヤカーの軽快さが発揮されるときだ(鶴岡市本町)
2009年(平成21年) 3月13日(金)付紙面より
ツイート森の新メニュー開発 中山間地の特産活用 つるおか元気プロジェクト 山王商店街が取り組み
鶴岡市の山王商店街の料理店や菓子店が、中山間地の食材を活用して開発した「森の新メニュー」の試食会が11日、市コミュニティプラザ・セントルで開かれた。温海地域特産の赤カブや、朝日地域のそば粉などを使ったオリジナルメニューが披露され、商品化などの可能性を探った。
つるおか森のキャンパス推進協議会(会長・佐藤正明鶴岡副市長)が進める「つるおか森のキャンパス元気プロジェクト」事業の一環。これまでプロジェクトでは市や民間団体、研究機関など14団体が連携し、森の産直カー事業などを展開している。同推進協に加盟する鶴岡山王商店街振興組合(三浦新理事長)は、昨年12月から中山間地の食材を活用した「山王食のブランド」開発に着手。地域農業者などの所得向上、商品の販売による商店街の活性化なども目的のひとつとして、同商店街の飲食店、菓子店計5店舗が新メニュー創作を進め、今回の試食会に合わせて「森の新メニュー」と名付けた。
この日は同商店街や市、生産者など関係者合わせて約25人が出席。山形大学農学部の江頭宏昌准教授が温海カブの葉を使って2006年に開発した「赤カブ葉パウダー」をめんに練り込んだうどん、カヤの実を使ったクッキー、朝日地域特産のソーメンカボチャのゴマ酢和え、朝日産のそば粉を団子状に練り豚肉を包んで揚げた「かいもち揚げ」など9品が発表された。
出席者たちはさっそく各メニューを皿に取り、味を確かめた。参加した20代女性は「赤カブ葉パウダーの豆乳蒸しがとてもおいしかった。カブの苦味が淡白な白身魚とよく合う」と気に入った様子。試食後は「うどんは和風のめんつゆで食べた方が大衆向けでは」「赤カブ葉のドレッシングは魚介類にも合いそうだ」など活発な意見交換があった。
同商店街振興組合は「試食会の意見を参考にするとともに、コスト面なども考慮しながら商品化を目指したい」と話していた。

山王商店街の飲食店、菓子店が開発した「森の新メニュー」の試食会
2009年(平成21年) 3月13日(金)付紙面より
ツイート本場職人からお墨付き 穂波街道緑のイスキア「真のナポリピッツァ」に合格
鶴岡市羽黒町押口のナポリピッツァ専門店「穂波街道緑のイスキア」(庄司祐子店長)が12日、イタリア政府公認の「真のナポリピッツァ協会」(アントーニオ・パーチェ会長)の認定審査に挑み、見事合格した。東北で初めて本場ナポリの認定店となった。
同協会は、ナポリピッツァの伝統技術を守り、後世に伝えることを目的に、地元のピッツァ職人たちが1984年に設立した。認定店となるには、協会が定める原材料(イタリアカンパーニア州産)を使用するなどの条件を満たし、生地の材料や配合、練り方、トッピングする材料の品質、焼き加減、味などの審査を受け正真正銘のナポリピッツァと認められた場合のみ許可される。これまで世界で約300店、日本で28店が認定されている。
この日、緑のイスキアで行われた審査には、同店ピッツァ職人の庄司建二さん(26)が臨んだ。同協会主任技術指導員のガエターノ・ファツイオさんら3人の審査員が見つめる中、手際良くピッツァを仕上げた。
審査終了後、ガエターノさんは「生地の扱いや焼き加減も良く、使っている素材の品質も良い。最終的に仕上がったピッツァの完成度が高かった」と評し、庄司さんに合格を告げた。庄司さんは「合格できてホッとしている。これからもイタリアの技術を守り、地元のお客さんに提供していきたい」と目に涙を浮かべながら喜びをかみしめていた。
認定式は来月東京都で行われ、協会の加盟店だけに与えられるロゴマークと世界共通番号が贈られる予定。
合格を目指しナポリピッツァ協会の認定審査に挑む庄司さん
- フリーペーパー

気になるお口の健康について、歯科医の先生方が分かりやすく解説します- 特集企画
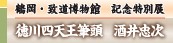
酒井家庄内入部400年を記念し、徳川家康の重臣として活躍した酒井家初代・忠次公の逸話を交え事績をたどる。
酒井家庄内入部400年を記念し、庄内藩中興の祖と称された酒井家9代・忠徳公の業績と生涯をたどる。
江戸幕府が3大名に命じた転封令。幕命撤回に至る、庄内全域で巻き起こった阻止運動をたどる。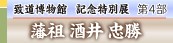
酒井家3代で初代藩主として、庄内と酒井家400年の基盤を整えた忠勝公の事績をたどる。
幕末~明治・大正の激動期の庄内藩と明治維新後も鶴岡に住み続けた酒井家の事績をたどる。
酒井家が藩主として庄内に入部し400年を迎えます。東北公益文科大学の門松秀樹さんがその歴史を紹介します。
教育現場に身を置く筆者による提言の続編です。
子どもたちを取り巻く環境は日々変化しています。長らく教育現場に身を置く筆者が教育をテーマに提言しています。
鶴岡市櫛引地域出身の大相撲の元横綱・柏戸の土俵人生に迫ります。本人の歩み、努力を温かく見守った家族・親族や関係者の視点も多く交えて振り返ります。
藤沢周平作品の魅力を研究者などの視点から紹介しています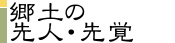
世界あるいは全国で活躍し、各分野で礎を築いた庄内出身の先人・先覚たちを紹介しています
旬の食べ物を使った、おいしくて簡単、栄養満点の食事のポイントを学んでいきましょう
庄内の「うまいもの」を関係者のお話などを交えながら解説しています