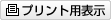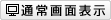- 音声ブラウザをご利用のお客様向けのリンクです。
- 本文へジャンプする
荘内日報ニュース
2024年(令和6年) 6月22日(土)付紙面より
ツイート土門拳記念館が新名称で再出発
「はじめ、ぼくも、東京の上野公園近くの、ある営業写真館の『門生』だった。拭き掃除、下足番、水洗いやハイポー(現像液)のかきまわし番といった営業写真的な実技を修業しながらも、そのまま営業写真家になってしまう気は、ぼくにはなかった」―。酒田市が生んだ写真家・土門拳の『ぼくの歩んだ道』(「土門拳 手 ぼくと酒田」)に載っている一文だ。
リアリズム写真を確立した写真界の巨匠と呼ばれる土門拳の全作品は、酒田市に寄贈され「土門拳記念館」に収蔵されている。その記念館の名称が2025年4月から「土門拳写真美術館」に変更される。土門作品の多様な芸術性に、より一層光を当てるためで、改称に伴う美術館のロゴマークを公募している。
◇ ◇
土門拳は6歳の時、酒田から家族で東京に移り住み、後に写真館で働いた。めったにない休日を利用して書店に出掛けて、写真に関する本を読みあさった。買った本は布団の中で読んで写真の知識を得たことで、土門は「自分に写真術の基礎を据えてくれたのは『寝床大学』だった」(同)と、世に出る前のことにも触れている。
土門が撮り続けた写真は、ありのままの現実にカメラを向ける「絶対非演出」だった。ライフワークだった「古寺巡礼」「室生寺」などはカメラを据えると一瞬差し込む光をひたすら待ち続けたという。また、著名人を撮った「風貌」では、自身が意図する表情を長時間待ち続けたことで、待たされた被写体が怒り出したというエピソードもある。
土門拳記念館のパンフレットに載っている「写真の立場」という土門の言葉である。「写真家は、機械のうしろに、小さくなっている。写真家が小さくなって、ついにゼロなってしまった時、すばらしい写真が撮れているようだ。ねらった通りにピッタリ撮れた写真は、一番つまらない。なんて間がいいんでしょうという写真になる」と。そのあたりにリアリズム写真に徹することになった原点があるのだろうか。
◇ ◇
土門拳記念館は1983年、日本初の写真を専門に展示する美術館として開館した。土門から寄贈を受けた全作品の保存を図りながら順次企画展を開いている。寄贈を受けた作品の中には、フィルムの劣化も心配される原版もあるため、現在デジタル化の作業も進めている。
長年慣れ親しんだ土門拳記念館の名称を土門拳写真美術館に変更する狙いは、20世紀の写真史に大きな足跡を残した土門拳の偉業を、今まで以上の視点で見てもらい、入館者増につなげたい意図もある。土門の言葉にある「写真は肉眼を越える」は、何度見ても新しい気付きがある、と言っているのではないだろうか。
ロゴマークの公募要項は、同記念館ホームページに。
- フリーペーパー

気になるお口の健康について、歯科医の先生方が分かりやすく解説します- 特集企画
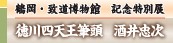
酒井家庄内入部400年を記念し、徳川家康の重臣として活躍した酒井家初代・忠次公の逸話を交え事績をたどる。
酒井家庄内入部400年を記念し、庄内藩中興の祖と称された酒井家9代・忠徳公の業績と生涯をたどる。
江戸幕府が3大名に命じた転封令。幕命撤回に至る、庄内全域で巻き起こった阻止運動をたどる。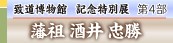
酒井家3代で初代藩主として、庄内と酒井家400年の基盤を整えた忠勝公の事績をたどる。
幕末~明治・大正の激動期の庄内藩と明治維新後も鶴岡に住み続けた酒井家の事績をたどる。
酒井家が藩主として庄内に入部し400年を迎えます。東北公益文科大学の門松秀樹さんがその歴史を紹介します。
教育現場に身を置く筆者による提言の続編です。
子どもたちを取り巻く環境は日々変化しています。長らく教育現場に身を置く筆者が教育をテーマに提言しています。
鶴岡市櫛引地域出身の大相撲の元横綱・柏戸の土俵人生に迫ります。本人の歩み、努力を温かく見守った家族・親族や関係者の視点も多く交えて振り返ります。
藤沢周平作品の魅力を研究者などの視点から紹介しています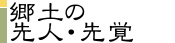
世界あるいは全国で活躍し、各分野で礎を築いた庄内出身の先人・先覚たちを紹介しています
旬の食べ物を使った、おいしくて簡単、栄養満点の食事のポイントを学んでいきましょう
庄内の「うまいもの」を関係者のお話などを交えながら解説しています