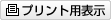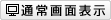- 音声ブラウザをご利用のお客様向けのリンクです。
- 本文へジャンプする
荘内日報ニュース
2008年(平成20年) 2月7日(木)付紙面より
ツイートある「イサバ」の一代 上
“決心”は母の一言
「イサバ」。浜で揚がったばかりの魚を、檀家(得意先)に行商して歩く女性のことだ。「浜のアバ」とも呼ばれる。産地直送のはしりでもあったイサバの登録と更新は一代限り。権利を他人に譲ることはできない。高齢化で昔ながらの風情を残す“食文化の配達人”は、いずれ姿を消す運命にある。エネルギッシュなイサバだが、歴史の一時期は悲哀が伴った。引退して2年。「今も檀家が気になる」という、鶴岡市鼠ケ関、五十嵐富美恵さん(89)に、一代を語ってもらった。
「子供を死なしぇでいらいねもんだ」―。実母のこの一言が、イサバになる決心をさせた。35歳の時だった。
1931(昭和6)年3月、念珠関第一尋常高等小学校尋常科を卒業。12歳で農業と漁業を営む自営業の家に子守り奉公に出た。同級生46人のうち、高等科に進んだのは数人。男は大工か左官か漁師、女は子守り奉公か一部は紡績工場に働きに出る。当時は半ば決まったコースで、大きな自営業者はどこも働き手不足を補うため、子守りを雇った。
「まだ12歳。子供が子供を子守しているようだった」と話す、住み込み奉公の手当は盆3円と正月の5円だけ。子供心に「手当は年2回しかもらえないもの」と思った。その手当も全部実家に渡し、何か自分の物を買った記憶はない。
子供の時から勉強が好きで、学校の成績も上位。夢は学校の先生。山形師範に進みたかった。「父は造船所の木挽き職人。2男2女の2番目。貧乏な暮らしに、(進学など)とても親に言い出せなかった。『及ばぬ鯉の滝登り』。自分にそう言い聞かせてあきらめるしかなかった。親を困らせてはならない。まず、家のことを立て、親孝行することが先。我慢することは当たり前、まして女はだった」
子守り奉公は16歳で辞めた。樺太で開業する鶴岡市の眼科医に同行し、窓口で事務の仕事をするためだ。勉強好きだったことを知る、知り合いの紹介だった。「稼ぐことができる」と、ためらいはなかった。
親に呼び戻され、20歳で製材所の勤め人と結婚。3男4女が生まれるが、4番目の二女を、生後すぐ急性肺炎で失う。
行商を始めたのは、53(昭和28)年正月。一番下の3男が生まれて3カ月後だった。今でこそ「一言でいえば食うに困ってのこと」と一笑するが、物もらいと間違われるのが嫌で嫌で、イサバになりたくない一心で、男がする山仕事、建設現場でもがむしゃらに働いた。
「イサバになれば現金収入になる。街(鶴岡市)で食べ物を手に入れることができることは分かっていても、恥ずかしくて、死んでも行商はしたくないと思っていた」
食糧難の時代。戦争や海で夫を亡くした女性たちは、資本もいらず、荷を背負う体力さえあれば身ひとつで商売できるイサバに走った。
家が農家なら物々交換もできたろうが、夫が給料取りではそれもできない。給料はもらっても、食べ物がなくては生きていけない現実がつきまとった。6人の子供がひもじい思いをしているのを見かねた実家の母から「子供を死なせる気か。育てるためには何でもしねばねもんだ」と、厳しく叱責(しっせき)される。
二女を亡くしたのは、食料も物資も困窮した44(昭和19)年。母の言葉が胸に突き刺さった。
(粕谷昭二)
メモ イサバの歴史は古い。「わが郷土鶴岡」(鶴岡市刊)では、庄内藩は城下の上肴町と下肴町(ともに現本町)に魚問屋を置いた。魚の需要が増えた1671(寛文11)年には他町内の「市の日」でも魚が売られ、触れ売りも自由になった。1784(天明4)年にはイサバの始まりとなる売り子が34人いた。浜から荷車で夜明け前に運んで来た魚は鮮度が良く「日通(ひどお)し」と呼ばれ、値も高かった。

藤島駅のホームで大きな荷物を背負って帰りの列車を待つ五十嵐さん=提供・五十嵐富美恵さん
- フリーペーパー

気になるお口の健康について、歯科医の先生方が分かりやすく解説します- 特集企画
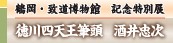
酒井家庄内入部400年を記念し、徳川家康の重臣として活躍した酒井家初代・忠次公の逸話を交え事績をたどる。
酒井家庄内入部400年を記念し、庄内藩中興の祖と称された酒井家9代・忠徳公の業績と生涯をたどる。
江戸幕府が3大名に命じた転封令。幕命撤回に至る、庄内全域で巻き起こった阻止運動をたどる。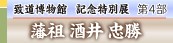
酒井家3代で初代藩主として、庄内と酒井家400年の基盤を整えた忠勝公の事績をたどる。
幕末~明治・大正の激動期の庄内藩と明治維新後も鶴岡に住み続けた酒井家の事績をたどる。
酒井家が藩主として庄内に入部し400年を迎えます。東北公益文科大学の門松秀樹さんがその歴史を紹介します。
教育現場に身を置く筆者による提言の続編です。
子どもたちを取り巻く環境は日々変化しています。長らく教育現場に身を置く筆者が教育をテーマに提言しています。
鶴岡市櫛引地域出身の大相撲の元横綱・柏戸の土俵人生に迫ります。本人の歩み、努力を温かく見守った家族・親族や関係者の視点も多く交えて振り返ります。
藤沢周平作品の魅力を研究者などの視点から紹介しています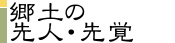
世界あるいは全国で活躍し、各分野で礎を築いた庄内出身の先人・先覚たちを紹介しています
旬の食べ物を使った、おいしくて簡単、栄養満点の食事のポイントを学んでいきましょう
庄内の「うまいもの」を関係者のお話などを交えながら解説しています