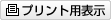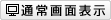- 音声ブラウザをご利用のお客様向けのリンクです。
- 本文へジャンプする
荘内日報ニュース
2011年(平成23年) 11月11日(金)付紙面より
ツイート森の時間46 ―山形大学農学部からみなさんへ―
今年も実りの秋がやってきました。おいしい果物や新米を味わえるとても幸せな季節です。今日は森から少し離れて、実のなる木の話をしようと思います。日本人の身近にあって、古くから親しい関係にある柿の話です。
柿と日本人の長くて深いつきあいの様子がよく現れている例として、みなさんもよくご存じの民話『さるかに合戦』があります。柿はこの物語の中でとても大切な役どころを演じています。忘れてしまったという方のために、ちょっと復習しますと…
気が短いサルは柿の種を拾ったのですが、種は食べることができないので、カニが持っていたおにぎりと交換します。心やさしいカニは、種をまいて毎日水をやり、大切に育てます。時が流れ、やがて柿の木は大きくなってたくさんの実をつけるようになりました。すると、ずるがしこいサルは、木に登れないカニの代わりに実を取ってやるふりをして、自分だけがおいしい実を食べ、カニには食べられない実を投げつけて意地悪をするのです。
思い出していただけましたか?
お話はまだ続くのですが、ここで問題です! この物語に登場する柿は、甘柿でしょうか、それとも渋柿でしょうか?
ヒントは物語の中に隠されています。次のようなシーンです。
サルは、実が色づきはじめた柿の木に登って、「真っ赤な」(または「おいしそうな」「熟れた」)実をむしゃむしゃと食べます。そして、木の下で待つカニには、「まだ青い」(または「まだ硬い」「渋い」)実を投げつけるというくだりです。
意地の悪いサルには本当に腹が立ちますが、じつはこの部分に重要な事実が描かれています。つまり、この民話に登場する柿の木には、一本の木の中に「熟れて、真っ赤になった、おいしい(渋くない)」実と「まだ青くて、硬くて、渋い(おいしくない)」実の両方が同時になっているのです。なぜなら、サルが渋い柿の実をがまんして食べたとは思えませんし、ブタだって渋を抜く前の柿の実はまたいで通りますから。
柿に甘柿と渋柿があることは誰でも知っていると思いますが、このように甘い実と渋い実の両方をつける柿の木はあるのでしょうか。
じつは、「ある」のです。「不完全甘柿」という柿です。このグループの柿は、実の中に種がたくさん(ふつうは数個以上)できたときは果肉全体にゴマ(褐斑といいます)が入って渋くなく(甘く)なります。しかし、種の数が少ない(ふつうは2―3個以下)ときは、ゴマは種の周囲だけにできて、その部分は渋くなくなりますが、他のところは渋いままで、全体としては渋柿になります。
実の中の種の数は受精のよしあしに左右されます。同じ木の中の実でも受粉や受精の状況によって種がたくさんできる実と少ししかできない実ができます。すると、種の多い実は大きくて、色づきもよく早く熟しますが、種の少ない実は小さめで、色づくのも遅れるのです。つまり、サルがおいしそうに食べたのは種の多い渋くない実で、カニに投げつけたのは種の少ない硬くて渋い実だったというわけです。
この柿の品種の名前までは残念ながらわかりません。『さるかに合戦』は越後地方の民話だといわれていますので、同地方の在来品種で不完全甘柿である妙丹柿や子成場などが候補にあがるかもしれません。しかし、新潟県ばかりでなくほぼ全国各地に不完全甘柿の在来品種は多数存在します(あるいは、していました)。不完全甘柿たちは私たち日本人にとってとても身近な柿なのです。
ちなみに、実の中にできる種の数の多少に関わらずに甘くなるタイプの柿は「完全甘柿」といい、よく知られた富有柿や次郎柿はこのグループに属します。
いずれにしても、昔の人たちは自分たちの身近にあった柿の木や実をよく見ていたのですね。その生活に根ざした鋭い観察力が『さるかに合戦』という民話に存分に反映されているといえるでしょう。柿と日本人のつきあいの深さをうかがい知ることができる一つの例だと思います。
(山形大学農学部教授、専門は園芸学および人間・植物関係学)
- フリーペーパー

気になるお口の健康について、歯科医の先生方が分かりやすく解説します- 特集企画
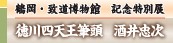
酒井家庄内入部400年を記念し、徳川家康の重臣として活躍した酒井家初代・忠次公の逸話を交え事績をたどる。
酒井家庄内入部400年を記念し、庄内藩中興の祖と称された酒井家9代・忠徳公の業績と生涯をたどる。
江戸幕府が3大名に命じた転封令。幕命撤回に至る、庄内全域で巻き起こった阻止運動をたどる。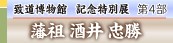
酒井家3代で初代藩主として、庄内と酒井家400年の基盤を整えた忠勝公の事績をたどる。
幕末~明治・大正の激動期の庄内藩と明治維新後も鶴岡に住み続けた酒井家の事績をたどる。
酒井家が藩主として庄内に入部し400年を迎えます。東北公益文科大学の門松秀樹さんがその歴史を紹介します。
教育現場に身を置く筆者による提言の続編です。
子どもたちを取り巻く環境は日々変化しています。長らく教育現場に身を置く筆者が教育をテーマに提言しています。
鶴岡市櫛引地域出身の大相撲の元横綱・柏戸の土俵人生に迫ります。本人の歩み、努力を温かく見守った家族・親族や関係者の視点も多く交えて振り返ります。
藤沢周平作品の魅力を研究者などの視点から紹介しています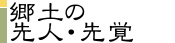
世界あるいは全国で活躍し、各分野で礎を築いた庄内出身の先人・先覚たちを紹介しています
旬の食べ物を使った、おいしくて簡単、栄養満点の食事のポイントを学んでいきましょう
庄内の「うまいもの」を関係者のお話などを交えながら解説しています